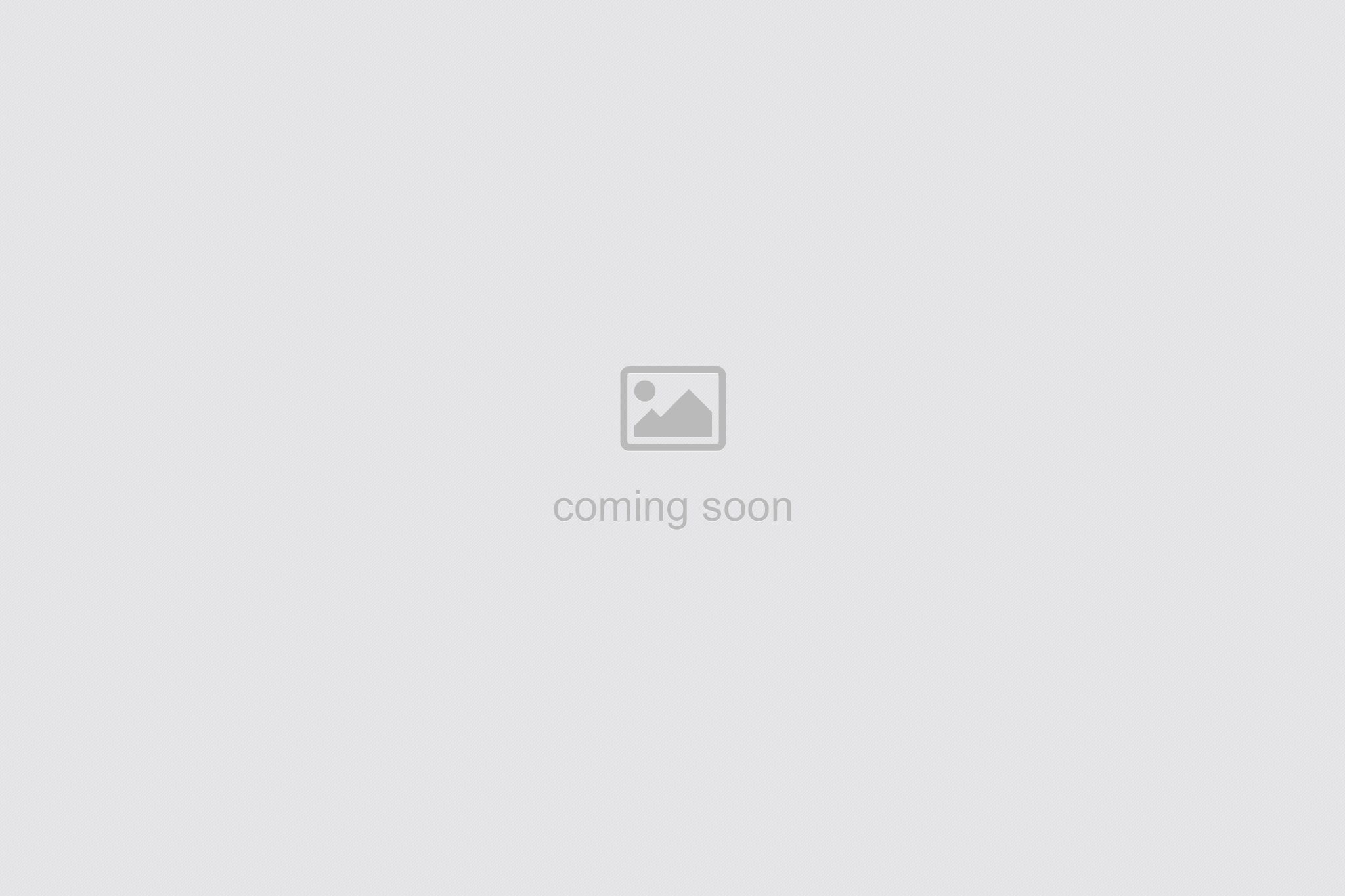6.『長者荘』を後にして
(清水歴史探訪より)
広大な別荘も住宅地に変わり、長者山の臨時駅のホームも、姿を消してしまいました。
しかし、井上馨が進めた柑橘栽培の研究は、現在JR興津駅に隣接する『独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構』の『柑橘研究興津拠点』として、果樹研究に重要な位置を占めています。
お話は柿沼守さんでした。
清水歴史探訪~~ 清水歴史探訪~~ 清水歴史探訪~~
お相手は石井秀幸でした。
この番組は、JR清水駅近く、さつき通り沿いの『いそべ会計』がお送りしました。『いそべ会計』について、詳しくはホームページをご覧ください。
帰ってから、改めて井上馨のことを調べてみました。山口県には井上馨の遺跡がたくさんあるようですが、すべて省略しました。貼り忘れた埋蔵文化財センターで取った写真1枚と、湯河原の 旧井上馨別邸の宿『清光園』の写真が参考になるかと思い、貼ってみました。
最後に、井上馨の出てくる教科書を参考に載せます。
国民学校国語教科書『母の力』
元治元年九月二十五日の夜である。
あと四年で明治維新(ゐしん)の幕が切つて落されようといふ時だ。天下の雲行きは、ほとんど息苦しいまでに切迫してゐる。
周防(すはう)の山口では、今日も毛利侯の御前會議で、氣鋭の井上聞多(ぶんた)が、反對黨を向かふにまはして、幕府に對する武備を主張した。堂々としたその議論に、反對黨は、ぐうの音も出なかつた。
その夜である。
下男淺吉の提燈(ちやうちん)にみちびかれながら、聞多が、山口の町から湯田の自宅へ歸る途中、暗やみの中に待ち受けてゐる怪漢があつた。
「だれだ、きみは。」
と、それがだしぬけに聲をかける。
「井上聞多。」と答へるが早いか、後に立つた今一人の怪漢が、いきなり聞多の兩足をつかんで、前へのめらせた。すかさず第三の男が、大刀を振るつて聞多のせなかを眞二つ。
それを、ふしぎにも聞多のさしてゐた刀が防いだ。うつ向けになつた際、刀がせなかへまはつてゐたのである。それでも、せ骨に深くくひ込む重傷であつた。
氣丈にも聞多は立ちあがつて、刀を拔かうとした。すると、一刀がまた後頭部をみまつた。更に、前から顔面を深く切り込んだ。
ほとんど無意識に、聞多はその場をうまくのがれた。あたりは眞のやみである。かれらは、なほも聞多をさがしたが、もうどこにも見つからなかつた。
多量の出血に、しばらくは氣を失つてゐた聞多が、ふと見まはすと、そこはいも畠の中であつた。からだ中が、なぐりつけられるやうに痛む。何よりも、のどがかわいてたまらない。
向かふに火が見える。聞多は、そこまではつて行つた。それは農家のともし火であつた。
「おお、井上の若旦那樣。どうしてまたこれは。」
驚く農夫に、やつと手まねで水を飲ませてもらつた聞多は、やがて農夫たちの手で自宅へ運ばれた。
淺吉の急報によつて、聞多の兄、五郎三郎は、押つ取り刀でその場へかけつけたが、もう何もあとの祭、どこにも人影はなかつた。弟の姿も見えない。再び家に取つて返すと、今農夫たちにかつがれて歸つた弟のあさましい姿。驚き悲しむ母親。
とりあへず、醫者が二人來た。しかし、聞多のからだは、血だらけ泥だらけである。醫者は、ばう然としてほとんど手のくだしやうも知らない。
聞多は、もう虫の息であつた。母・兄・醫者の顔も、ぼつとして見分けがつかない。からうじて一口、
「兄上。」
とかすかにいつた。兄の目は、涙でいつぱいである。
「おお、聞多。しつかりせい。敵はだれだ。何人ゐたか。」
たづねられても、聞多には答へる力がなかつた。ただ、手まねがいふ。
「介錯(かいしやく)頼む。」
兄は、涙ながらにうなづいた。どうせ助らない弟、頼みに任せてひと思ひに死なせてやるのが、せめてもの慈悲だ。決然として、兄は刀を拔いた。
「待つておくれ。」
それは、しぼるやうな母の聲である。母の手は、堅く五郎三郎の袖にすがつてゐた。
「待つておくれ。お醫者もここにゐられる。たとへ治療のかひはないにして
も、できるだけの手を盡くさないでは、この母の心がすみません。」
「母上、かうなつては是非もございませぬ。聞多のからだには、もう一滴の
血も殘つてゐませぬぞ、手當てをしても、ただ苦しめるばかり。さあ、お
はなしください。」
兄は、刀を振りあげた。
その時早く、母親は、血だらけの聞多のからだをひしとだきしめた。
「さあ、切るなら、この母もろともに切つておくれ。」
この子をどこまでも助けようとする母の一念に、さすが張りつめた兄の心もゆるんでしまつた。
聞多の友人、所郁太郎(ところいくたらう)が、その場へかけつけた。かれは、蘭方(らんぱう)醫であつた。
かれは、刀のさげ緒をたすきに掛け、かひがひしく身支度をしてから、燒酎(せうちう)で血だらけの傷を洗ひ、あり合はせの小さな疊針で傷口を縫ひ始めた。聞多は、痛みも感じないかのやうに、こんこんと眠つてゐる。ほかの醫者二人も、何くれとこの手術を手傳つた。かうして、六箇所の大傷が次々に縫ひ合はされた。
それから幾十日、母の必死の看護と、醫者の手當てとによつて、ふしぎにも一命を取り止めた聞多が、當時の母の慈愛の態度を聞くや、病床にさめざめと泣いた。
それを、ふしぎにも聞多のさしてゐた刀が防いだ。うつ向けになつた際、刀がせなかへまはつてゐたのである。それでも、せ骨に深くくひ込む重傷であつた。
氣丈にも聞多は立ちあがつて、刀を拔かうとした。すると、一刀がまた後頭部をみまつた。更に、前から顔面を深く切り込んだ。
ほとんど無意識に、聞多はその場をうまくのがれた。あたりは眞のやみである。かれらは、なほも聞多をさがしたが、もうどこにも見つからなかつた。
多量の出血に、しばらくは氣を失つてゐた聞多が、ふと見まはすと、そこはいも畠の中であつた。からだ中が、なぐりつけられるやうに痛む。何よりも、のどがかわいてたまらない。
向かふに火が見える。聞多は、そこまではつて行つた。それは農家のともし火であつた。
「おお、井上の若旦那樣。どうしてまたこれは。」
驚く農夫に、やつと手まねで水を飲ませてもらつた聞多は、やがて農夫たちの手で自宅へ運ばれた。
淺吉の急報によつて、聞多の兄、五郎三郎は、押つ取り刀でその場へかけつけたが、もう何もあとの祭、どこにも人影はなかつた。弟の姿も見えない。再び家に取つて返すと、今農夫たちにかつがれて歸つた弟のあさましい姿。驚き悲しむ母親。
とりあへず、醫者が二人來た。しかし、聞多のからだは、血だらけ泥だらけである。醫者は、ばう然としてほとんど手のくだしやうも知らない。
聞多は、もう虫の息であつた。母・兄・醫者の顔も、ぼつとして見分けがつかない。からうじて一口、
「兄上。」
とかすかにいつた。兄の目は、涙でいつぱいである。
「おお、聞多。しつかりせい。敵はだれだ。何人ゐたか。」
たづねられても、聞多には答へる力がなかつた。ただ、手まねがいふ。
「介錯(かいしやく)頼む。」
兄は、涙ながらにうなづいた。どうせ助らない弟、頼みに任せてひと思ひに死なせてやるのが、せめてもの慈悲だ。決然として、兄は刀を拔いた。
「待つておくれ。」
それは、しぼるやうな母の聲である。母の手は、堅く五郎三郎の袖にすがつてゐた。
「待つておくれ。お醫者もここにゐられる。たとへ治療のかひはないにして
も、できるだけの手を盡くさないでは、この母の心がすみません。」
「母上、かうなつては是非もございませぬ。聞多のからだには、もう一滴の
血も殘つてゐませぬぞ、手當てをしても、ただ苦しめるばかり。さあ、お
はなしください。」
兄は、刀を振りあげた。
その時早く、母親は、血だらけの聞多のからだをひしとだきしめた。
「さあ、切るなら、この母もろともに切つておくれ。」
この子をどこまでも助けようとする母の一念に、さすが張りつめた兄の心もゆるんでしまつた。
聞多の友人、所郁太郎(ところいくたらう)が、その場へかけつけた。かれは、蘭方(らんぱう)醫であつた。
かれは、刀のさげ緒をたすきに掛け、かひがひしく身支度をしてから、燒酎(せうちう)で血だらけの傷を洗ひ、あり合はせの小さな疊針で傷口を縫ひ始めた。聞多は、痛みも感じないかのやうに、こんこんと眠つてゐる。ほかの醫者二人も、何くれとこの手術を手傳つた。かうして、六箇所の大傷が次々に縫ひ合はされた。
それから幾十日、母の必死の看護と、醫者の手當てとによつて、ふしぎにも一命を取り止めた聞多が、當時の母の慈愛の態度を聞くや、病床にさめざめと泣いた。